こんにちは、整体療術院UPです。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉は耳なじみがありますが、実際に「お彼岸とは何か?」を深く考える機会は少ないかもしれません。今回は日本に古くから伝わるお彼岸について、整体の視点とも重ねながらお伝えします。
🪷 お彼岸の意味
「彼岸」とは仏教の言葉で、「あちらの岸=悟りの世界」を表します。
一方、私たちが暮らす現実世界は「此岸(しがん)=こちらの岸」と呼ばれます。
春分・秋分の時期は、太陽が真東から昇り、真西に沈みます。西は極楽浄土がある方向とされ、この時期は 「彼岸と此岸がもっとも近づく特別な期間」 と考えられてきました。
そのため、先祖供養や自分自身を見つめ直す大切な習慣として「お彼岸」が広まりました。
🌅 なぜ「お彼岸」というの?
本来は「彼岸」といいますが、日本語では大切な行事や仏事には敬意を込めて「お」をつけます(お盆・お正月などと同じ)。
だから「お彼岸」と呼ばれるようになったのです。
🌱 お彼岸にすること

- お墓参りや仏壇参りで、ご先祖への感謝を伝える
- 季節の節目に、自然の恵みに感謝する
- お供えとして「おはぎ」や「ぼた餅」をいただく
🍡 おはぎとぼた餅の違い
お彼岸のお供え物といえば「おはぎ」と「ぼた餅」。
実はどちらも同じ「もち米+あんこ」の食べ物ですが、呼び名とイメージする花が季節によって変わります。
- 春のお彼岸:ぼた餅
春に咲く「牡丹(ぼたん)」にちなんで「ぼた餅」。
小豆の粒あんを牡丹の花に見立てることもあります。 - 秋のお彼岸:おはぎ
秋に咲く「萩(はぎ)」にちなんで「おはぎ」。
小豆のこしあんを萩の花になぞらえる場合もあります。
つまり、名前は違っても本質は同じ。
自然の花と季節を大切にしてきた日本人の感覚が息づいている食文化なんですね。
🌱 季節の節目に、自然の恵みに感謝する
お彼岸はちょうど 季節の大きな変わり目 にあたります。
春のお彼岸では「これから芽吹く命の力」に感謝し、秋のお彼岸では「実りや収穫の恵み」に感謝する――そんな役割を担ってきました。
日本人は昔から、自然とともに生き、季節の移ろいをとても大切にしてきました。
例えば、春は田植えや種まきの時期にあたり、秋は収穫の喜びを味わう時期です。
その区切りに先祖を敬い、自然に手を合わせることは、「人は自然の一部である」という感覚を思い出す時間でもあったのです。
そしてこれは現代を生きる私たちにとっても大切な視点です。
- 季節の変化に合わせて体は揺らぎやすい
- 気温や日照時間の変化が心身のリズムに影響を与える
- だからこそ「自然に逆らわず、調和して暮らす」ことが健康の土台になる
整体で体のバランスを整えるのも、まさにこの自然の流れに沿って生きるため。
お彼岸は、自然と人との結びつきをもう一度思い出す機会なのです。
🌿 六波羅蜜を日常に
お彼岸では「六波羅蜜(ろくはらみつ)」という6つの心がけも意識します。
- 布施…分け合う心(席を譲る・笑顔を向ける)
- 持戒…約束を守る(ルールやマナーを大切に)
- 忍辱…怒りに振り回されない(深呼吸して受け流す)
- 精進…小さな努力を続ける(毎日のストレッチ)
- 禅定…心を落ち着ける(静かな時間をもつ)
- 智慧…本質を見抜く(相手の立場も考えてみる)
これは特別な修行ではなく、毎日の暮らしを少しずつ整えるためのヒントです。
🌀 整体と通じる視点
お彼岸が「心を調える」時間だとすれば、整体は「体を調える」時間。
実際には心と体はひとつにつながっているので、どちらか片方だけでなく両方を意識することが大切です。
- 体が整うと、呼吸が深まり、気持ちが安らぐ。
- 心が安らぐと、自然と体もゆるむ。
お彼岸をきっかけに心を見つめ直すことは、整体で体を整えることと同じように、より自然で健やかな自分に近づくことにつながります。
✨ まとめ
お彼岸とは、
- 自然の恵みに感謝する
- ご先祖を敬い思い出す
- 自分の心と体を調える
そんな日本に古くから続く大切な習慣です。
この秋のお彼岸、季節の味である「おはぎ」をいただきながら、ほんの少し自分やご先祖に思いを向けてみませんか?
それは、体を整えて日々を心地よく過ごす整体の考え方とも、どこか通じるものがあると思います。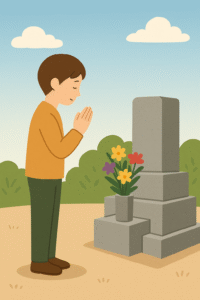
整体療術院UP
新潟市秋葉区北上2-13-9
☎ 0250-22-5973
顕上 義宗(けんじょう よしむね)
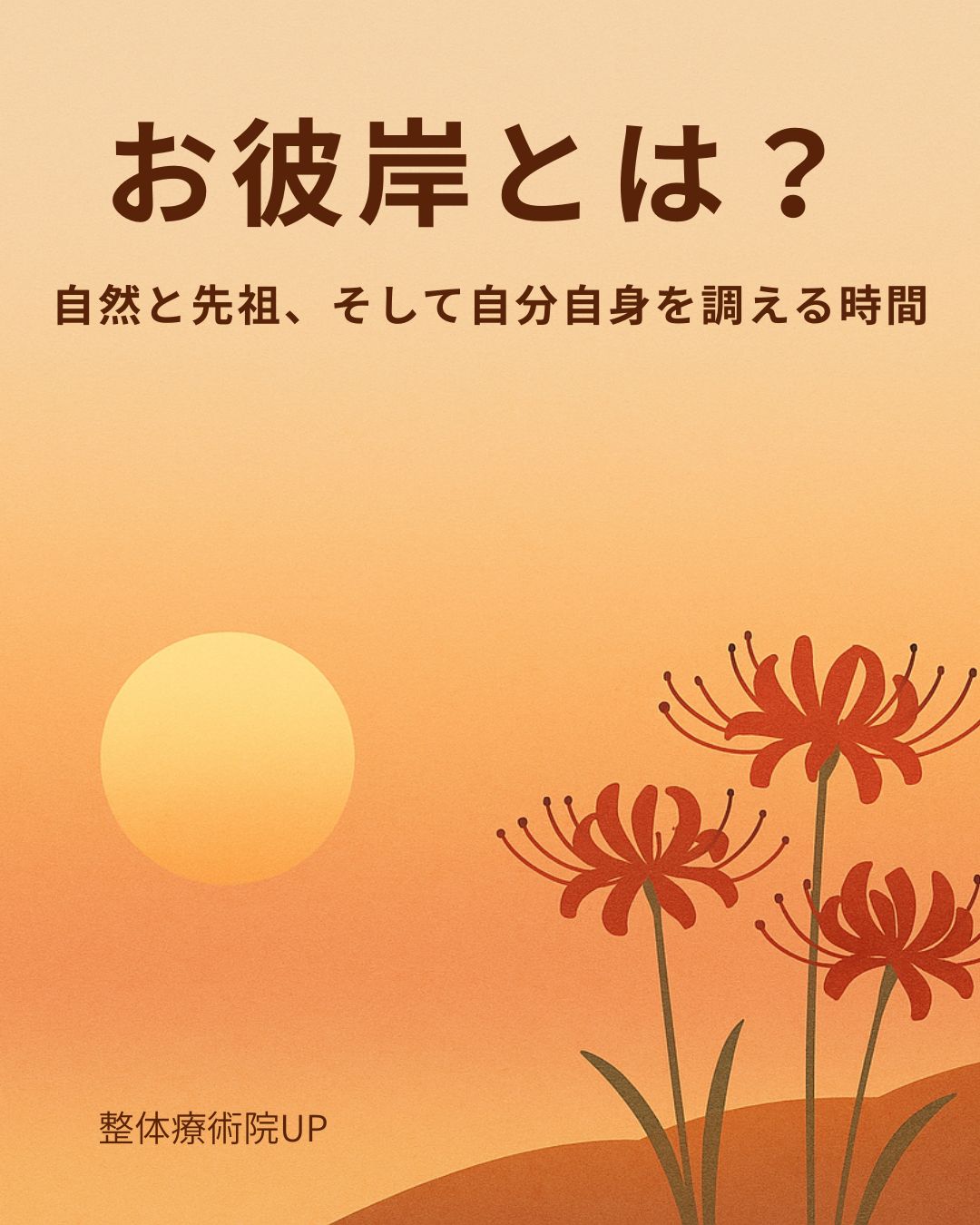

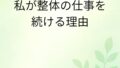
コメント